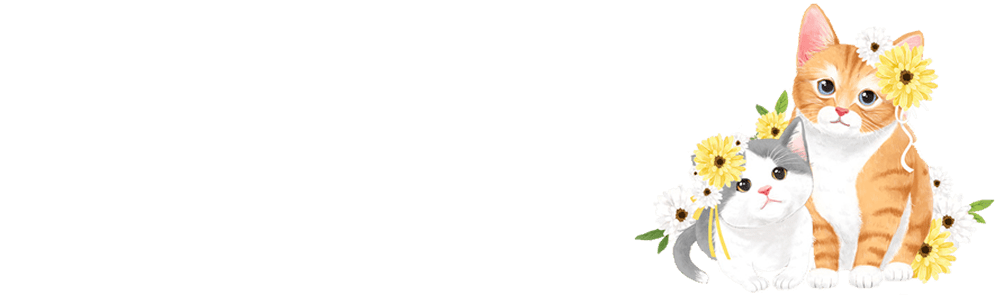当記事はプロモーションが含まれています
猫の病気について

猫の健康を守ることができるのは私たち飼い主だけです。
しかし、いざ症状が表れるとあたふたするばかりで動物病院に駆け込むというケースが少なくありません。
特に腎臓病を含む猫の尿トラブル(尿路結石)は、オス・メス問わず発症しやすいことで知られています。
症状が深刻な場合は手術が行われることもありますが、軽症であれば薬の服用と療法食で改善することもあります。
ここでは、飼い主が発見できる尿路結石の予兆や尿路結石を予防するフード選びと与え方についてもお話します。
尿路結石の他にも、猫がかかりやすい代表的な病気と症状についてもまとめました。動物病院に行く前に予備知識があると落ち着いて獣医師の話を聞くことができますからぜひ参考にしてください。
猫がかかりやすい病気
猫がかかりやすい、猫カリシウイルス感染症、猫白血病ウイルス感染症、猫汎白血球減少症、猫伝染性鼻気管炎、猫クラミジア感染症はワクチンの接種で予防することができます。
飼育環境や病気の流行地域によって3種〜7種混合ワクチンを選べますが、一般的な家庭の完全室内飼いであれば3種混合ワクチンが勧められることがほとんどです。
ワクチンの効果は永久に続くものではありません。年に1回(1歳未満は年2回)の接種で病気を予防しましょう。
猫がかかりやすい皮膚の病気
- アレルギー性皮膚炎
- ノミアレルギー
- 皮膚糸状菌症
などは、かゆみ、湿疹、ただれなどが主な症状です。塗り薬やステロイド剤が処方されることがありますが、原因になっているアレルゲン、ノミ、菌を取り除くことが大切です。
- 心因性脱毛
- ホルモン失調性皮膚疾患
などは脱毛が主な症状です。猫は環境の変化が苦手で、引越し等をきっかけに脱毛してしまうことがあります。甲状腺などホルモンの分泌異常は、左右対称に脱毛するのが特徴です。自己判断で塗り薬などは使わずに動物病院で診察を受けてください。
- 毛包炎
- デモデックス症
いずれも猫ニキビやニキビダニ症と呼ばれることがあります。毛穴に詰まった分泌液があごの下に黒い斑点に見えたり、ニキビダニが原因でフケ、かさぶた、脱毛の症状が表れたりすることがあります。ニキビダニを駆除する薬浴で治療が行われます。
猫がかかりやすい耳の病気
- 耳ダニ症
- 外耳炎
耳を痒がったり頻繁に頭を振ったりします。黒い耳垢が多い場合は耳ダニ症が疑われます。耳ダニ症は殺ダニ剤で治療します。
外耳炎はダニ、細菌、アレルギーなどが原因で耳をかくことで炎症が広がり、膿みやかさぶたの症状が表れることも。
原因をによって治療法は異なりますが、中耳や内耳に炎症が広がる前に治療をすすめるのが望ましいとされています。
猫がかかりやすい目の病気
- 結膜炎
- 角膜炎
健康な猫の目は透き通っていいますが、目ヤニや涙が多かったり炎症が起きたりしている時は異常のサインです。
結膜炎は、猫ヘルペスウイルスや猫カリシウイルス感染症が原因のこともあり感染症の治療が行われることがあります。
角膜炎はケンカの傷や目に入った異物が原因のことがあります。炎症を抑える治療が行われます。
- 流涙症
常に涙が出ている症状は流涙症の可能性があります。涙の刺激でまばたきの回数が増えたり眩しがったりすることがあります。
ペルシャやヒマラヤンのような鼻の低い猫がかかりやすい代表的な目の病気です。
猫がかかりやすい呼吸器の病気
- 上部気道感染症(猫風邪)
鼻から咽頭までの鼻腔に炎症が起こります。
鼻水、くしゃみ、涙目などの症状が起こることから猫風邪と呼ばれることが多いのですが、カリシウイルス、猫コロナウイルス、クラミジア、マイコプラズマなどウイルスや細菌による感染症であることがほとんどです。混合ワクチンで予防することが大切です。
- 下部気道感染症
気管支や肺に炎症が起こります。咳、呼吸困難などの症状が見られます。
上部気道感染症と同じようにウイルスや細菌による感染が主な原因です。肺に寄生する猫肺虫や肺毛細線虫が原因のこともあります。
猫がかかりやすい消化器の病気
- 猫汎白血球減少症
- 猫コロナウイルス感染症
下痢や嘔吐の症状が表れる代表的な猫の感染症です。症状の度合いによって治療法が異なります。
多頭飼いしている場合は隔離や消毒で感染が広がらないようにしましょう。
猫がかかりやすい泌尿器の病気
- 尿路結石(尿結石症)
- 膀胱炎
腎臓、膀胱、尿道など尿の排泄を司る器官の病気は猫に多くみられます。
尿路結石は特によくかかる病気で、特普段から水分補給できる工夫をしたりマグネシウムの配合量を抑えたフードで尿のpHを酸性に保つといった心がけが予防につながります。
膀胱炎の主な原因は細菌ですが、尿路結石が膀胱炎を起こすこともあります。症状が軽い場合は薬の服用やフードの切り替えで改善することがありますが、結石が大きくなっている場合は手術が行われます。
猫がかかりやすい血液の病気
- 溶血性貧血
ヘモバルトネラ症やレプトスピラ症など感染症の他、ネギやたまねぎなどの中毒が原因で赤血球が減少し起こる貧血です。
原因を特定し症状に合った治療が行われます。
- 自己免疫性溶血性貧血
免疫抗体が赤血球を攻撃してしまうことで起こります。
詳しい原因はまだ分かっていないそうですが、猫の場合は猫白血病ウイルスに感染した猫の発生が多いといわれています。
猫がかかりやすい心臓の病気
- 心筋症
心筋が厚くなる肥大型心筋症、心筋が薄くなって心臓が大きくなる拡張型心筋症、心臓が広がらない拘束型心筋症の3つのタイプに分かれます。
先天性の疾患のことも多い心筋症ですが、拡張型心筋症は肥満が原因になることがあります。
増えている猫のがん
90年代初頭、猫の寿命は10年ぐらいといわれていました。2016年現在、日本ペットフード協会の発表では猫の平均寿命は15.75歳となっています。
完全室内飼いで感染症リスク、ケガ・事故による死亡リスクが減ったこと、キャットフードで栄養をバランス良く補えるようになったことが背景にあるようです。
しかし、ご長寿猫が増えるのと同時にがんを患う猫も増えていることが指摘されています。
- リンパ腫
- 乳腺腫瘍
- 皮膚腫瘍
- 扁平上皮がん
- 肥満細胞腫
などがあります。
猫の場合、悪性の腫瘍であることが多いため早期発見、早期治療が重要とされています。
しかし、治療を開始しても肺や腹部への転移が認められたり、化学療法の副作用が強く出たりし完治が難しいのが現実です。
猫エイズについて
猫免疫不全ウイルス感染症(猫エイズ)は、ウイルスに感染し免疫力が低下することで様々な感染症に侵される病気です。
ウイルスに感染しても発症しなければ元気なまま天寿をまっとうすることもありますが、発症した場合の致死率ほぼ100%といわれています。
猫どうしのケンカなどの咬傷で感染することが多いので、完全室内飼いで野良猫との接触を防ぐことが大切です。
日本では2008年から猫免疫不全ウイルス感染症のワクチンが導入されています。
ワクチンの接種で70%以上感染を防ぐことができるというデータがあるようですが、有効性についてはまだわからないとする専門家もいます。
猫の尿路結石ができる原因
猫下部尿路疾患(FLUTD)は、膀胱から尿道の間で起こる様々な病気のことを指しています。
猫下部尿路疾患の中でも代表的なのが猫の尿路結石(尿結石症)です。
尿路結石の主な原因
猫の尿路結石は、マグネシウムが由来のストルバイト結石とカルシウム由来のシュウ酸結石の2種類に分かれます。
キャットフードに含まれるミネラル成分が影響したり、尿のpHが偏ったりすることが尿路結石の原因のひとつとされています。
結石はごく小さな砂粒程度のものから、手術で取り除く必要がある数ミリから数センチの固まりまで様々です。
砂漠がルーツとされる猫はもともとあまり水を飲まず、成分が凝縮された濃い尿をする傾向があります。このことも結石ができる原因とされています。
尿路結石はオス・メス問わず発症します。オスの場合尿道がカーブし細くなっていことも尿路結石の原因といわれています。
尿路結石の症状
猫がトイレに行ってもうずくまってなかなかおしっこが出ない、おしっこをする時に痛がる、トイレに間に合わず粗相を繰り返すなど、おしっこのトラブルが表れている時は尿路結石が疑われます。
2日以上排尿がないと尿毒症になる可能性が高まり、点滴や手術などの処置を行わなければ命に関わることもあります。
尿路結石の症状が現れる前に、頻繁に水を飲んだり猫砂に結晶のような結石がキラキラと混じったりする兆候が見られることがあります。
気づいたらすぐに診察を受けてください。
尿路結石の治療
症状が軽い場合は、結石を溶かす薬を服用したり尿のpHをコントロールする療法食に切り替えたりして経過を見ます。
結石が大きかったり症状を繰り返したりする場合は手術が行われることがあります。
深刻な症状を抱えたオスの場合、ペニスを切断して尿道を広げる手術が行われることもあります。
尿路結石の予防と対策
水分の摂取量を増やすことが大切です。流水が好きな猫には流水式の給水器を利用する方法があります。
ドライフードはお湯でふやかしたり、猫缶やパウチタイプのフードを取り入れたりしても良いでしょう。
キャットフードのラベルをチェックすると、トウモロコシや小麦などの穀物類が多く使われているものが多いことに気づきます。
このようなキャットフードは猫の尿をアルカリ性に傾けることがあり、猫下部尿路疾患の猫の尿もアルカリ性を示します。
健康な猫の尿は弱酸性を示すため、尿を酸性に整える肉類が多く含まれているキャットフードを選ぶことがポイントです。
ぜひ、猫の生態に合った肉類が主原料のキャットフードを選んであげてください。
キャットフードによるアレルギー

猫は犬よりもフードによるアレルギーは少ないといわれています。
しかし、この頃はキャットフードによるアレルギーに悩む猫が増加傾向にあるそうです。
本来、猫が穀物類を自分の意思で食べることはありません。しかしキャットフードにはトウモロコシや小麦などの穀物類が多く使われています。穀物類は、かさ増しして原料費を安く抑えたり、カロリーを抑えたりするために使われることが多いようです。
猫は肉食動物ですが牛肉、豚肉、鶏肉、ラム肉などの肉類がアレルギーの原因になることもあります。特に牛肉や豚肉は猫がアレルギーを起こしやすい食材として知られています。
- 湿疹、かゆみ、脱毛
- 嘔吐、下痢
このように皮膚に症状があらわれる場合や、嘔吐や下痢といったお腹に症状があらわれる場合があります。発熱や外耳炎を起こすこともあります。
キャットフードによるアレルギーの治療
血液検査などでアレルギーが疑われる場合、アレルギーの原因と考えられる食材を取り除いた食事に切り替えます。
飼い主の自己判断で行うと栄養バランスが崩れる心配があるため獣医師の指導の下で、様子を見ながらキャットフードを切り替えていきます。
アレルギーの原因になりやすい食材を使っていないキャットフードから試していくことが多いのですが、原因をつきとめるまで時間がかかることがあります。
皮膚の炎症や外耳炎が起きている場合は治療薬が処方されますが、アレルゲンを特定できないとこれらの症状が長引くこともあります。
粗悪なキャットフードでアレルギーのような症状が出ることも
キャットフードの原料の穀物類に農薬が多く使われていいたり、人工添加物がたくさん使われていたりすることが原因で、猫にアレルギーのような湿疹、脱毛、嘔吐、下痢といった症状が出る可能性があると指摘する専門家がいます。
猫の生態に合った高品質のキャットフードに切り替えると症状が改善されたケースがあるそうです。
発がん性が指摘され人間への使用が禁止されている酸化防止剤(BHT、BHA)を使ったフードが流通していることから、全てのキャットフードが猫の健康を考えているとは言い切れないのが現実です。
アレルギー検査を受けても結果が陰性という場合は、もしかしたらフードに問題があるのかもしれません。
人にうつる猫の病気
人にうつる猫の病気もあるので気を付けましょう。
人獣共通感染症とも呼ばれるズーノーシスは動物から人へ感染する病気があります。
有名なのは狂犬病やエキノコックスですが、猫から人にうつる病気もあるので注意が必要です。
猫引っかき病やパスツレラ症は免疫力が低下していると症状が悪化しやすいといわれています。
高齢者や小さなお子さんが猫に触れる場合は見守りをしたり、規則正しい生活を心がけて免疫力が衰えないように気をつけたりすることも大切です。
トキソプラズマ症について
トキソプラズマは単細胞の寄生虫で、感染するとトキソプラズマ症と呼ばれます。
トキソプラズマは鳥や哺乳類に寄生し一生を宿主の体内で過ごすとされています。しかし猫がトキソプラズマに感染すると糞と一緒にトキソプラズマが排出されます。
そのため、猫を飼っている家の猫トイレ(猫砂)や猫が糞をした公園の砂場などが感染源になることがあります。
通常、トキソプラズマに感染しても何も症状が現れないとされています。
しかし妊娠中に初めてトキソプラズマに感染すると、胎盤や羊水から赤ちゃんにも感染することがあります。赤ちゃんに感染すると、流産、死産、水頭症、視力障害などの原因になることがあります。
自分がトキソプラズマに感染しているかどうかは血液検査で調べることができます。
猫を飼っている場合やガーデニングなどで土いじりをする機会が多い場合は、トキソプラズマ抗体検査が含まれているブライダルチェックを受けても良いでしょう。
すでに妊娠している場合は、猫砂の掃除は家族に代わってもらったり公園の砂遊びやガーデニングは控えるようにすると安心です。
猫引っかき病について
猫の爪に棲んでいる最近や微生物が、猫に引っかかれた時に傷口から侵入しリンパ節が腫れる病気のことをいいます。
軽度であれば自覚症状がないうちに治ってしまうことがありますが、発熱や関節痛の症状が出て治療が終わるまで数週間かかることもあります。
子どもがかかりやすいといわれています。野良猫や人に慣れていない猫を触らないように普段から言い聞かせて予防しましょう。
パスツレラ症について
およそ80%の猫が口内に保有しているパスツレラ菌は、人間に感染すると風邪のような症状があらわれます。
糖尿病、喘息といった病気を抱えている方や高齢者が感染すると肺炎に進行し、深刻な場合では死に至ることもあります。
猫とキスをしたり、同じお箸を使って餌を食べさせたりすると感染リスクが高まりますから、濃厚なスキンシップは控えましょう。
関連ページ
- 猫を飼う前に揃えておきたいグッズ15選
- 初めてネコを飼うと決まったら!猫に必要なグッズが揃っているかチェックしてみましょう。
- 猫の予防接種
- 猫の予防接種に義務はある?そもそも猫の予防接種は義務なのかという疑問を抱いたことはありませんか。
- 猫のしつけってできる?
- 猫の困った行動は程度の差こそあれ多くの飼い主さんが悩んでいるのではないでしょうか。
- 猫の好きな食べ物
- 猫は人間の食べ残しをもらうことが多く、国によって猫が好きだと思われている食べ物は違うようです。